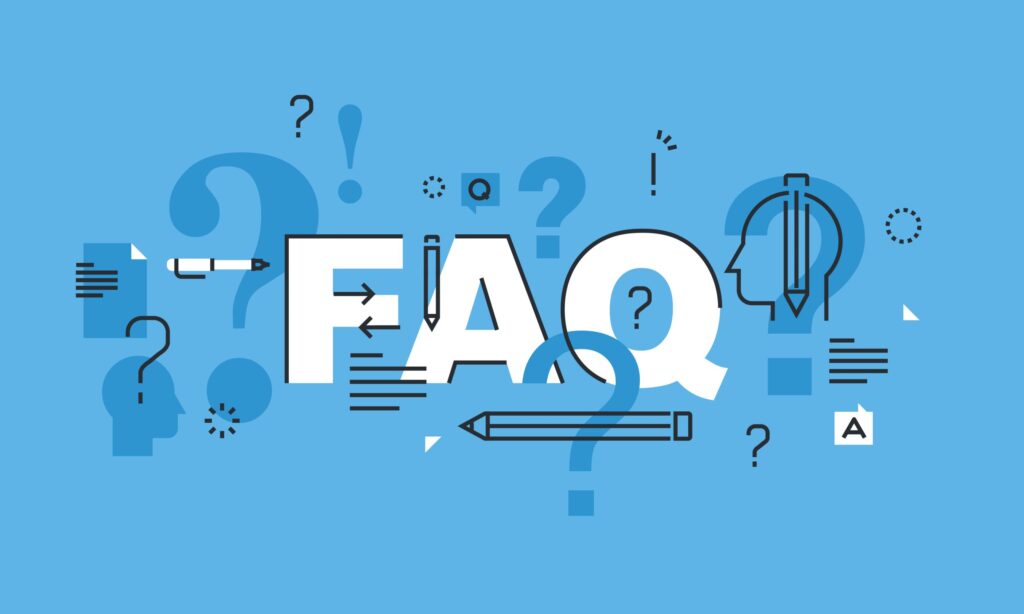こんにちは。
ラッセルベッドフォードの澤柳です。
今回は、これまでお送りしているニュースレターに関し、よくいただくご質問とその回答を3つ選び、皆さんへ共有させて頂こうと思います。
皆さんにも当てはまるケースがあるかもしれませんので、最後までお読み頂ければ嬉しいです。
【質問1】
自己資本比率(*) など計算し理解はしていますがどのように現場のスタッフへ落とし込めば良いでしょうか?
(*) 自己資本比率とは総資本(負債+純資産)のうちどれだけ自己資本(=純資産)が割合を締めているかを表す指標です。
【回答1】
分析は経営者の仕事ですので、その分析結果を従業員へ必ずしも共有する必要はありません。その一方で従業員に共有するのは、その分析指標をもう少し噛み砕いた指標、例えばKPIなどにしてあげます。分析結果を次の改善行動に移すことが目的で従業員へ情報共有するので、比率などではなく、彼らが「自分の責任」として捉えられる数字を伝えなければいけません。
例えば自己資本比率を例に考えてみると、自己資本比率は自己資本(純資産)と他人資本
(負債)に分解されます。
つまり、自己資本比率を上げることが第1目標ならば、他人資本を減らすか自己資本を上げるかしか方法はありません。自己資本は主に資本金や繰越利益剰余金で構成されていますので、自己資本を上げるためには増資をする、または利益をコツコツ上げる、という第2の目標ができます。
一方、他人資本を減らすということに関しては、負債総額を減らすことが目標となりますので、例えばサプライヤーへの支払タームを短くする、借入金を早めに返していく、といったことが第2の目標となります。
そうすると、この自己資本比率を上げるという目標の中で、経営者の責任範囲は
1 増資の検討
2 サプライヤーへの支払いターム検討
3 借入金返済スケジュールの検討
であり、従業員の責任範囲は利益を上げることに限定されています。
よって従業員への情報共有は会社としていくら利益を出さないといけないか、そのためにどのような努力が必要か、であり、自己資本比率を上げるために一緒に頑張ろう、では決してありません。
自己資本比率をここでは例に出しましたが、他の比率や指標であっても同じです。必ず従業員が自分の責任と捉えられる数字まで分解してから共有するようにしましょう。
特に財務分析で使う比率は、このように細かく分解できるようになっていますので、使う比率に応じて皆さんでもどのように分解できるか一度確認してみてください。
【質問2】
会社の月次決算に毎月1ヶ月ほどかかっており、財務分析をしても2ヶ月前のことになるなので、あまり意味がないと感じています。
【回答2】
財務分析というよりは月次決算に1ヶ月かかるという事の方が非常に大きな問題です。
決算書ではない別の情報をもとに当月利益や財務状況の把握をしているのだと思いますが、それでは不十分です。経営の意思決定が伴う限り、当月利益や会社の財務状況を把握するためには必ず月次決算書を使ってください。
決算書がないと、売上や利益といった情報は仮に入手できたとしても、分析はできません。分析にはBSとPLの両方が必要です。そもそも経営者の意思決定に必要な財務情報は翌月の1日時点で既に表に出ていますので、月次決算を翌1営業日で行うことも不可能ではありません。
外部報告のための決算書は確かに精度が必要で時間はかけて頂いても構いませんが、経営者が使う決算書に関しては精度よりもスピードの方が重要です。財務諸表が完璧でなくても会社は潰れませんが意思決定の遅れによって会社は潰れることがあります。
決算を早めるためには、例えば、売上や費用に関しては日々適時で入力。小口現金管理として定額資金前渡制度の導入。請求書の届いていない費用については見込みで一時的に計上しておく。請求書が届いた時に実際の数字へ修正。
原価計算結果におかしな数字が出てしまい、解決に時間がかかる場合は見積原価を一時的に計上しておく。解決した時に正しい原価へ修正。
棚卸しは材料を30日、仕掛品と完成品を31日に実施し、31日時点の材料在庫は理論値で算出。など、、、
経営者の意思決定に影響を与えない範囲で、経理にも余計な負担をかけない程度の会計処理を行うことはいくらでも考えられます。経理に1営業日で決算書を出して欲しい、といきなりお願いすれば断られることは必至です。こういう方法で決算できないか、と経理へ相談して一緒に決算スピードを早める方法を考えてみましょう。
【質問3】
赤字が続いており、財務的にも苦しいです。BSはまだまだ改善が必要ですが、とりあえずPLの黒字化をするための会計的アプローチはありますでしょうか。
【回答3】
経理が作成するPLだけでは、どうPLを改善するべきか見えづらいと思います。
その根本的原因は、PLが変動費と固定費に分けて記載されていないことにあります。PLの構成要素は、究極的には以下の4つです。
P・・・売上単価
Q・・・売上数量
M・・・変動費単価
F・・・固定費
この4つのバランスにより、利益は以下のように計算されます。
利益=PQ(売上)−MQ(変動費)−F(固定費)
つまり、利益を上げるにはこの4つの要素をうまくコントロールする必要があるということがわかります。
PLをパッと見るとたくさんの科目が記載され何が原因でその利益となったのかが見えにくいはずです。それは私でも同じです。
PLをこの4つの要素だけで見れば、4つの要素の絶対値
損益分岐点売上高
損益分岐点比率
粗利率や変動比率
労働分配率や労働生産性
などを確認して事業構造の把握ができ、どうして赤字なのかも容易に理解できます。
売上単価か、売上数量か、変動費か、固定費かの4つのどこに問題があるのか探すだけで良いのです。問題がどこにあるかがわかれば、あとは改善に移すのみです。
さて、最新のSSTおよび印紙税の動向についてのオンラインセミナーを9月24日(水)14時~15時にオンラインで開催することが確定しました。
今回は以上となります。
今週も一緒に頑張っていきましょう!